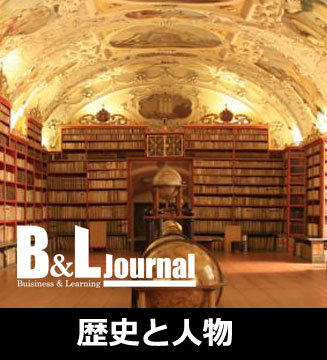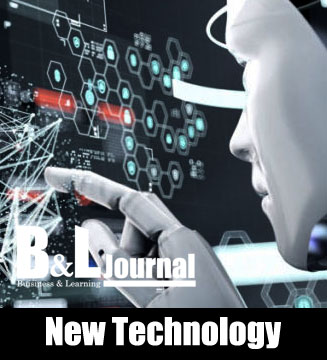関西空港を運営する関西エアポートによると、2022年に国際線を利用した旅客数は約235万人と、1994年の開港以来最も少なかった2021年に比べて9倍以上に増えた。ただ、過去最多を記録したコロナ禍前の2019年比では、わずか約9%にとどまっている。
新型コロナウイルスの水際対策が大幅に緩和された2022年10月以降、韓国、台湾などを中心に航空需要の回復が進んでいるものの、コロナ禍以前に全体の3割近くを占めていた中国からの利用者はいぜんとして低調で、その先行きは全く見通せない。
22年世界粗鋼生産4.2%減 ゼロコロナの中国で減少
中国BYD 日本でEV乗用車 第1弾SUVから販売開始
グローリー ベトナム・ダナン市に現地法人設立
東京・渋谷の東急百貨店本店,立川高島屋 営業終了
メディカロイド 手術支援ロボの保険適用を拡大
日産自・ルノー 15%の対等出資で近く合意へ
JTB 23年の国内旅行コロナ禍前の9割まで回復
JTBが消費者へのアンケートや国の統計「などをもとに行った2023年の旅行需要予測によると、今年国内旅行に出かける人はコロナ禍前の2019年の9割程度まで回復する見通し。具体的には1泊以上の国内旅行に出かける人は延べ2億6,600万人で前年より8.6%増え、2019年の91.2%まで回復すると見込まれる。政府の「全国旅行支援」なども後押しする。一方、海外旅行に出かける人は前年の3倍近くまで増えるものの、2019年比では40%程度に留まるとしている。
また、日本を訪れる外国人旅行者数2,110万人で前年比5.5倍に急増し、2019年比66%程度まで回復すると見込む。ただ、大きな比重を占めてきた中国人旅行者の動向が、同国政府の政治的要素で先行き不透明なことから見通せず、これによって振れ幅が大きくなりそうだ。
大阪本社の製薬3社が共同輸送開始 混載で効率化
エーザイ アルツハイマー病新薬 優先審査品目に指定
トヨタ 3年連続で世界販売首位 22年も1,000万台超
三菱ケミカルGと三井化学 共同物流へ検討開始
パナソニックHD 自動車部品国内外14拠点でCO2ゼロ
トヨタ 14年ぶり社長交代 後任は佐藤執行役員
独メルセデスが米国で初の「レベル3」自動運転車
日本製鉄など3社 海外CCSの協働で覚書を締結
日本製鉄、三菱商事、エクソンモービルの3社は1月26日、豪州などの海外アジアパシフィック圏内でのCO2回収・貯留(CCS)、およびCCSバリューチェーン構築に向け共同検討に関する覚書を締結したと発表した。
3社は日本製鉄の国内製鉄所から排出されるCO2の回収に関する調査や必要な設備開発の評価を行い、エクソンモービルによる豪州およびマレーシア、インドネシアをはじめとする海外アジアパシフィック圏でのCO2貯留先の調査、および三菱商事による海外へのCO2輸送およびCCSバリューチェーン構築に向けた評価を実施していく。
日本でのCO2回収・海外でのCO2貯留に関するCCSバリューチェーン構築の具体的な検討は世界で初めての取り組みとなる。
22年ロボット受注1.6%増 3年連続増加で最高更新
エーザイ 認知症薬「レカネマブ」欧州で申請受理
スズキ 電動車開発に30年度までに2兆円投資
日本調剤 23年内全薬局の電子処方箋化へ運用開始
日本のGDP ドイツに抜かれ4位転落の可能性
米国、中国に次ぎ世界3位の日本の名目国内総生産(GDP)が4位に転落する可能性が出てきた。ロシアのウクライナ侵攻を契機に、新型コロナからの回復途上の世界経済がまたも減速を余儀なくされ、先行きは見通せないが、遅くとも5年以内に、早ければ2023年にもドイツに抜かれ4位に転落する可能性が出てきた。近年の円安に伴うドルベースの経済規模の縮小に加え、低成長が経済を蝕(むしば)んだためだ。
国際通貨基金(IMF)の経済見通しでは2022年の名目GDP(予測値)は、3位の日本が4兆3,006億ドル(約555兆円)。これに対し4位のドイツのGDPは4兆311億ドルで、ドイツが約6.7%増えれば逆転することになる。
IMFの予測では2023〜2027年も辛うじて逆転は免れる。だが、2023年時点(予測値)でその差は6.0%に縮小する。日本のエコノミストらは、企業の労働生産性や国際競争力を高める政策をテコ入れしなければ、遅くとも5年以内にはドイツに抜かれる可能性は高いと警鐘を鳴らしている。
外食22年売上13.3%増も飲酒業態はコロナ前比半減
日本フードサービス協会のまとめによると、2022年の外食産業の全体売上は前年比13.3%増となったが、夜間外食需要と企業の宴会需要は戻らず、コロナ禍前の2019年比ではいぜんとして5.8%減の水準。中でも飲酒業態は2019年比で50.8%減の水準に留まっている。
2022年の業種別売上状況をみると、「ファミリーレストラン」は前年比18.1%増、2019年比16.2%減、「ディナーレストラン」は同31.7%増、同23.4%減、「喫茶」は同16.8%増、同20.0%減、「パブレストラン・居酒屋」は同80.9%増、同50.8%減となっており、店内飲食業態は回復基調にあるものの、コロナ禍前の水準には戻っていない。
一方、「ファーストフード」は同7.9%増、同8.6%増と、引き続き洋風を中心にテイクアウト、デリバリーを下支えに売上好調を維持している。
スカイドライブ「空飛ぶクルマ」米で26年就航目指す
次世代の輸送機「空飛ぶクルマ」および「物流ドローン」の開発を進めているスタートアップ、スカイドライブ(本社:愛知県豊田市)は1月25日、米サウスカロライナ州で空港と市街地の間を運航、2026年に就航を目指すと発表した。
アリゾナ州のメサで開催された2023年度のeVTOLシンポジウムで、この米国市場への参入計画と、サウスカロライナ州に本拠点を置いたことを明らかにした。
2026年に空飛ぶクルマ「SD-05」の運航開始を目指して、さらなる協業・提携のネットワークを構築していくとともに、サウスカロライナ州の政府機関や自治体と協力し、コロンビア・メトロポリタン空港とグリーンビル・ダウンタウン空港、2つの空港をを起点としたユースケースの構築に重点を置いて活動する計画。
印マルチ・スズキ SUVを中南米へ輸出開始第一弾
ホンダ 米国での四輪車生産累計3,000万台を達成
ホンダ(本社:東京都港区)は1月24日、米国現地法人アメリカン・ホンダモーター(本社:カリフォルニア州トーランス)が、2023年1月をもって米国での四輪車生産累計3,000万台を達成したと発表した。同社は1959年に二輪車、1970年に小型四輪車のそれぞれ販売を開始。
1982年に日本の自動車メーカーとして初めて、米国オハイオ州での四輪乗用車生産となる「アコード」の生産を開始し、その後もアラバマ州、インディアナ州と米国での生産体制を拡大するとともに、カナダやメキシコでの生産も開始している。
また、今後の本格的なEV(電気自動車)生産に向けて、オハイオ州内の3つの既存工場に合計7億米ドルを投じ生産設備を更新し、これらの工場を北米におけるEV生産のハブ拠点として進化させていくとしている。
22年全国百貨店売上高13.1%増 コロナ前の9割回復
東洋エンジ インドネシアで地熱発電所を受注
東洋エンジニアリング(本社:千葉県習志野市、以下、TOYO)は1月24日、インドネシア関連会社Inti Karya Persada Tehnik(イカペテ、以下、IKPT)が、コンソーシアムパートナー、PT Multi Fabrindo Gemilong(マルチファブリンドグラミン、以下、MFG)とともに、PT Medco Cahaya Geothamal(メドコチャハヤジオサーマル、MCG)が計画する地熱発電所プロジェクトを受注したと発表した。
同プロジェクトは東ジャワ州初の地熱発電所となる。2024年12月完成予定。設計、調達、建設、試運転の一括請負。対象設備は発電システム31.4MW、地上蒸気システム(SAGS)、送電線システム150KV。
TOYOおよびIKPTは今後も持続可能な社会の実現およびインドネシアの経済発展に貢献していく。